
遺産分割とは
被相続人の所有していた財産は、原則として、相続が開始と同時に相続人全員の共同所有(遺産共有)となります(民法898条)。
遺産共有は、一つの物の上には一つの所有権しか存在しない(このような考え方を『一物一権主義』といいます。)という考え方と矛盾するものではありませんが、いずれ共有状態は解消されるべきであることを考えれば、あくまで暫定的な状態といえるでしょう。
相続開始時において、被相続人が作成した遺言書がある場合には、原則としてその遺言書に記載された内容に従って遺産の帰属が決められます(指定相続分)。
一方、遺言書がない場合には、個々の財産について相続人全員による話し合いでもって誰の所有物とするかを決めるべきことになります。
共同相続人全員の話し合いによって遺産の配分に関して取り決めをすることを『遺産分割協議』といいます。
遺産分割協議には、必ず相続人全員が参加しなければならず、相続人の一部を除外した遺産分割協議は無効となります。
ところで、民法の考え方には、『法定相続分』というものがあり、例えば妻は2分の1、子は2分の1など、相続する割合が決まっています。
この法定相続分は、法律が定めた各相続人の遺産に対する分配の基準となるべきものにすぎません。
したがって、相続人全員が合意して遺産分割をする限りこの法定相続分に従う必要はなく、どのようにして遺産を分配するかは、最終的には相続人全員の合意により自由に決めることができます。
遺産分割の方法
遺産分割の代表的な方法には、現物分割、代償分割、換価分割があります。
いずれの方法によるべきかは、それぞれの状況によるべきことになります。
1.現物分割
現物分割とは、各相続人が取得する財産を個別に決める方法です。
たとえば、「配偶者が預金を相続する」「長男はA土地を相続する」「二男はB土地を相続する」というように、相続人それぞれが取得する財産をありのままの状態で分割する方法です。
現物分割は、遺産分割の方法としては、もっとも一般的な方法といえます。
また、現物分割の例として、たとえば「長男と二男がA不動産を2分の1の割合で相続する」などというように、共有で相続することもできます。こうしておくことで、後日、A不動産を売却する際には、売却代金も2分の1の割合で分配することが可能となります。
2.代償分割
共同相続人のうちの一部の相続人が財産を現物で取得し、その代わりに財産を取得しなかった他の相続人に対して、その相続分に相当する財産を「代償金」として自己の現金などを用いて支払う方法です。「代償金」はあくまで財産を取得する相続人から他の相続人に対して支払われるものであって「贈与」されるものではないため、贈与税の課税対象とはなりません。
この方法は、たとえば特定の不動産や被相続人が経営していた会社の株式などを特定の後継者に集中させたい場合等のケースで有効な遺産分割の方法です。
ただし、代償分割によるときは、財産を相続する相続人から他の相続人し、代償金としての現金を用意する必要があることから、財産を相続する相続人にとって大きな負担が生じることがあります。また、代償金を支払う側としては、その財産の評価を低く抑えたいと考え、他方、代償金を受け取る側としては、その財産の評価を少しでも高くしたいと考えることもあるでしょうから、この点を巡り双方の意見が合致するか否が成否のポイントとなります。
3.換価分割
財産の一部(または全部)を売却し、遺産を現金化したうえで、その換価代金を相続人間で分割する方法です。
現金を遺産分割の内容どおりに公平に分配することができるというメリットがあります。
ただし、売却までに時間を要する場合や、売却そのものが容易でない財産(たとえば、農地など)の場合、換価分割による遺産分割は難しいことがあります。
遺産分割協議が成立したら

遺産分割協議が成立した場合には、その協議の内容を記載した『遺産分割協議書』を作成します。
遺産分割協議書は、誰が、どの財産を、どのように相続するかを相続人全員が話し合って決めた結果を記した文書であり、相続人同士の一種の契約書といえるものです。
遺産分割協議は相続人全員が参加することを要し、一部の者を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。
もっとも、相続人全員が協議の内容を了解し遺産分割協議書に署名押印等を行えば、一堂に会して遺産分割協議を作成することまでは必要ではありません。したがって、遺産分割協議書に持ち回りで署名押印をすることなどは問題ありません。
法律的には、遺産分割協議書を作成することは必要不可欠なものではないのですが、実務上は、相続手続全般において遺産分割協議書(印鑑証明書付)の提出を求められますので、遺産分割協議が成立した場合には、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないといってよいでしょう。
なお、平成30年の民法改正により、遺産分割による場合に限らず、法定相続分を超えて遺産を相続した場合には、その旨の登記・登録等をしない限り、第三者に対抗(主張)することができないこととされました。したがって、遺産分割協議によって法定相続分と異なる形で相続することとなったにもかかわらず長期間登記等をしないでいると、第三者との関係において思わぬトラブルが生ずることがありますのでご注意ください。
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
遺産分割協議が必要となるケース
- 土地や建物の名義変更登記(相続登記)
- 預貯金の解約や名義変更
- 株式などの有価証券の名義変更
- 自動車などの登録動産の名義変更
- 相続税の申告
遺産分割協議書が不要なケース
- 法定相続分どおりに相続する場合
- 調停や審判により遺産分割がなされた場合
- 遺言書があり、遺言書どおりに相続する場合
- 法定相続人が一人しかいない場合
- 遺産分割協議の対象になるような財産がない場合
遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
100人の相続人がいるとして、そのうちたった1人だけでも同意しない相続人がいるのであれば、他の99人が同意していても、遺産分割協議は成立しません。
つまり、多数決などによって遺産分割協議が成立することはありません。必ず、全員の合意が必要です。
そして、通常の相続人同士の話し合いによって遺産分割について意見がまとまらない場合、まずは家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立て、調停によって解決を図ることになります。
『調停』は裁判所が関与する相続人の「話し合い」です。実際の調停の場では、調停委員会が双方から事情を聴いた上で、納得できる解決策を見出していきます。無事に合意ができた場合には、調停が成立し、事件は終了となり、作成された調停調書によって、各相続人は遺産分割の手続を行うことになります。
結果的に『調停』がまとまらなかった場合(調停不成立)、『審判』に移行します。
この審判においては、調停のときのように相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が公平に配慮した上で、審判を下して強制的に遺産分割をします(家庭裁判所の下した審判に不服がある当事者は、即時抗告という不服申立の機会は与えられます)。
なお、通常の金銭をめぐるトラブルなどの場合には、調停の申立などせず、いきなり訴訟といった形で相手を訴えることもできますが、遺産分割の場合には、まずは必ず調停を申立て、調停が不成立の場合に限り、審判に持ち込むことができるものとされています。
遺産分割の取消し・無効
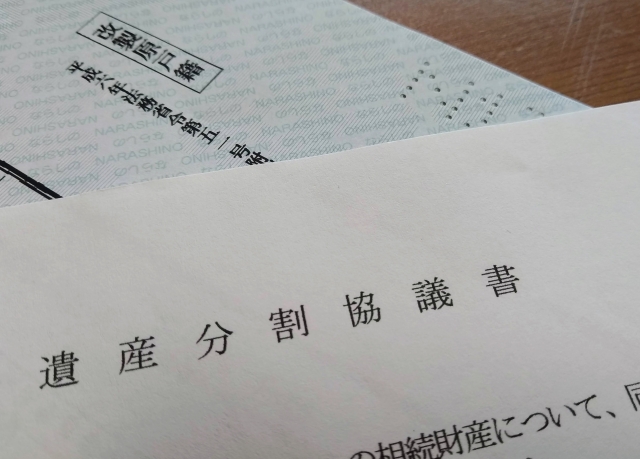
遺産分割協議について一定の原因がある場合、一旦は成立した遺産分割協議が取り消されたり、無効となったりすることがあります。
ただし、遺産分割協議の取消しについては、一般原則に従い、追認することができる時(取消しの原因に気が付いた時)から5年、行為の時遺産分割協議が成立してから20年を経過すると主張することができなくなります。
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
1.詐欺・強迫による遺産分割協議
遺産分割は相続人間の一種の契約にほかなりませんから、遺産分割協議において第三者による詐欺や強迫があり、それによって遺産分割が成立したのであれば、後に取消すことができます。また、強迫により完全に意思の自由を失って遺産分割をしたのであれば、その遺産分割協議は無効となります。
2.錯誤による遺産分割協議
たとえば、被相続人が遺言を残していたことを知らないまま相続人間で遺産分割協議を行った場合において、もし、遺言があることやその内容を知っていれば、遺産分割協議には応じなかったというようなケースであれば、遺産分割の意思表示について法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があったとして、遺産分割協議の取消しを主張することができます。
なお、民法改正前の規定では、錯誤による場合には『無効』であるとされていましたが、『無効』であれば本来的には誰かでも主張することができるところ、錯誤による無効については意思表示をした本人に限り主張することが許され、第三者が主張することができないものとされていたことから(取消的無効)、『無効』とはいいながらも実質的には『取消し』にすぎないと考えられていました。そこで、民法の改正により、錯誤の場合についても『無効』ではなく『取消し』の対象となるものと改められることとなりました。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
3.一部の相続人を除外した遺産分割協議
遺産分割協議は、必ず相続人全員の合意により行われることを要します。したがって、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議の解除
1.債務不履行による解除
遺産分割協議によって、相続人の一部の者が他の相続人に対して義務(債務)を負担することがあります。
たとえば、長男が実家の不動産を相続する代わりに母の面倒を見る、といった内容(条件)で遺産分割協議をしたのに、実際には長男が母の面倒を見なかった、といったケースのように、遺産分割協議によって約束した債務が履行しなかったときに、通常の契約違反のように遺産分割協議を「債務不履行」を理由として解除できるか否かという問題があります。
この点について最高裁判所は「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条(債務不履行)によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である」と判断しました(最判平元.2.9)。
つまり、債務不履行を原因として遺産分割協議を解除することはできません。
2.相続人全員の合意による解除
では、いったん成立した遺産分割協議を相続人全員の合意によって解除し、改めて遺産分割協議をすることはできるでしょうか。
この点について最高裁判所は「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない」と判断しました(最判平2.9.27)。
つまり、いったん相続人間で有効な遺産分割協議が成立している場合も、相続人全員の合意があればこれを解除し改めて遺産分割協議をすることができます。
ただし、法律上、遺産分割協議を相続人全員の合意により解除することは妨げられませんが、税務上は「無効原因の伴わない単純な遺産分割協議のやり直しを原因とする財産の移転については、相続による承継ではなく相続人が取得した遺産の贈与であると扱われる点に注意が必要です(相基通19の2-8)。このような税務上の取り扱いによれば、一回目の遺産分割は相続手続の一環として行われたものと扱われる反面、2回目の遺産分割は相続人間で贈与があったものとして、贈与税の課税の対象となってしまうのです。ですから、遺産分割協議のやり直し、といった事態は極力避けるよう、慎重な判断のもとで遺産分割をすべきでしょう。
